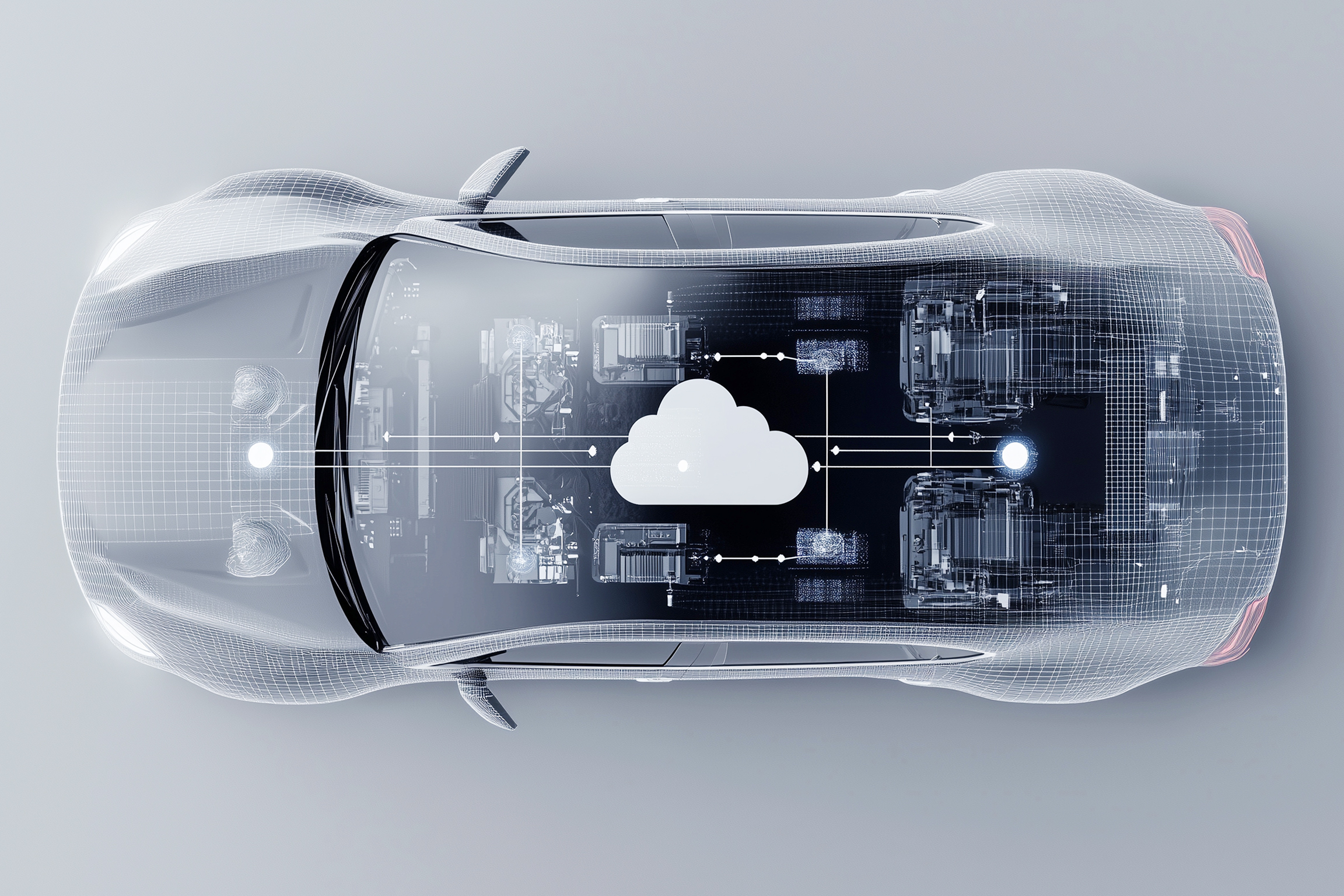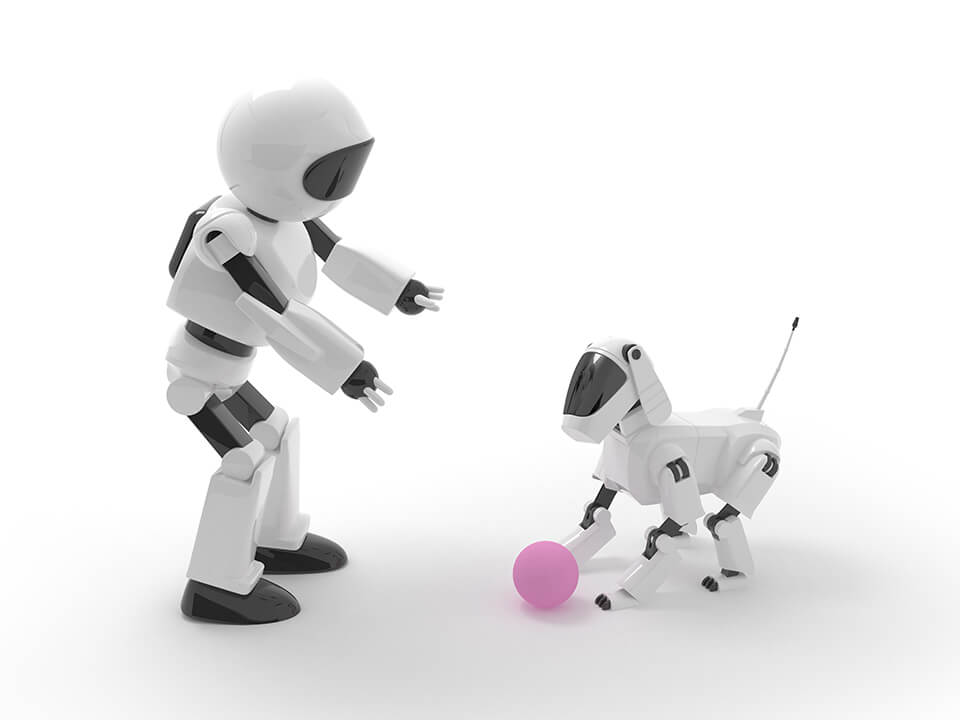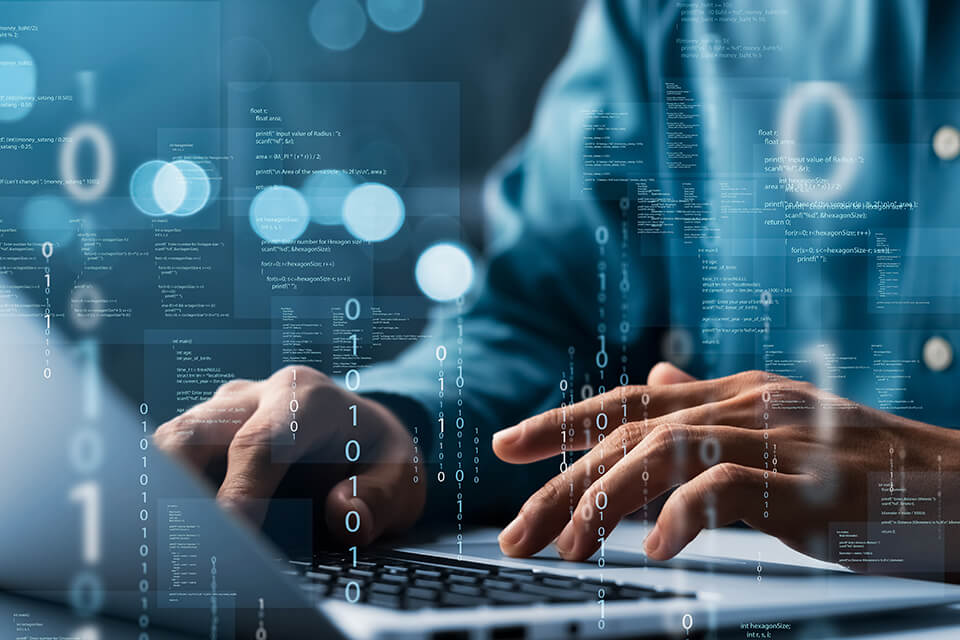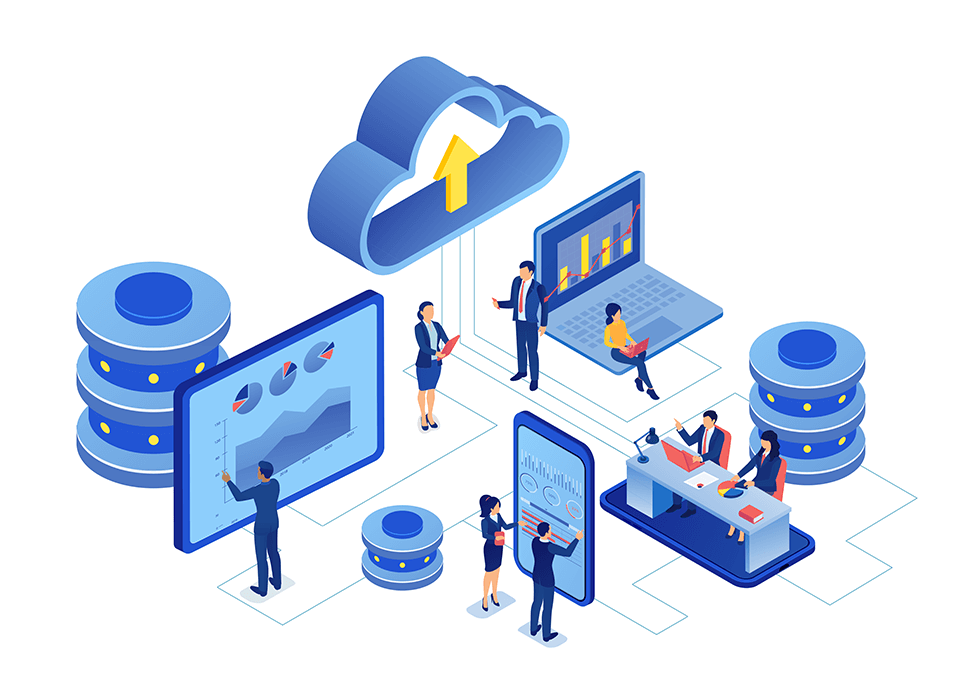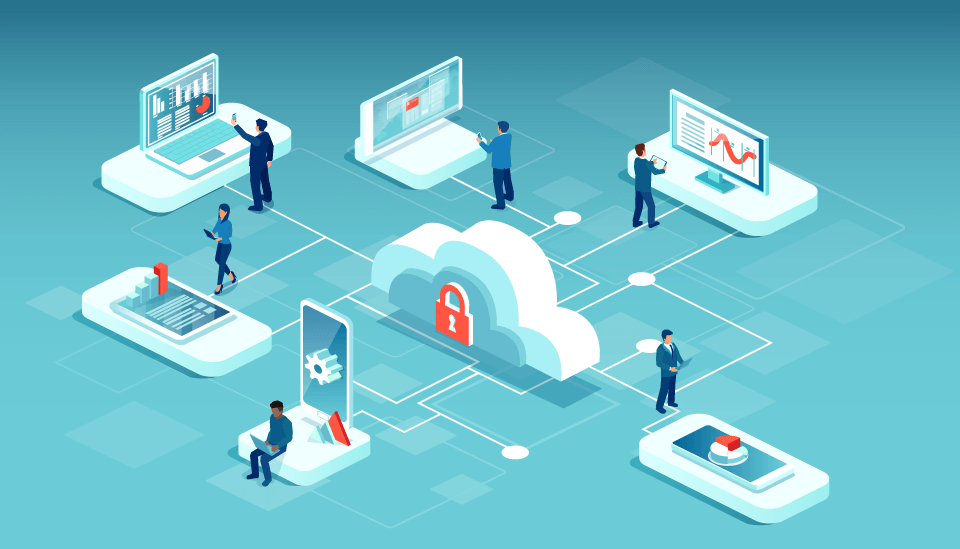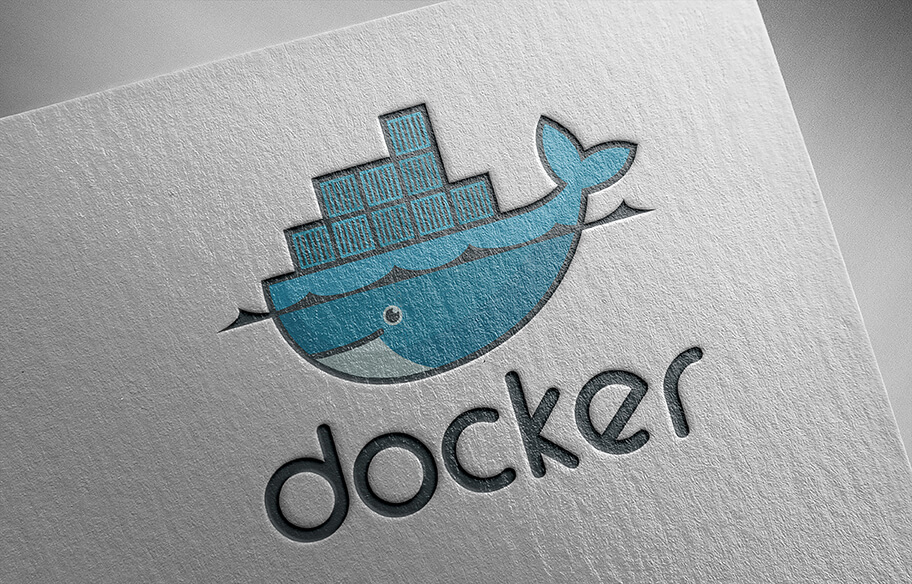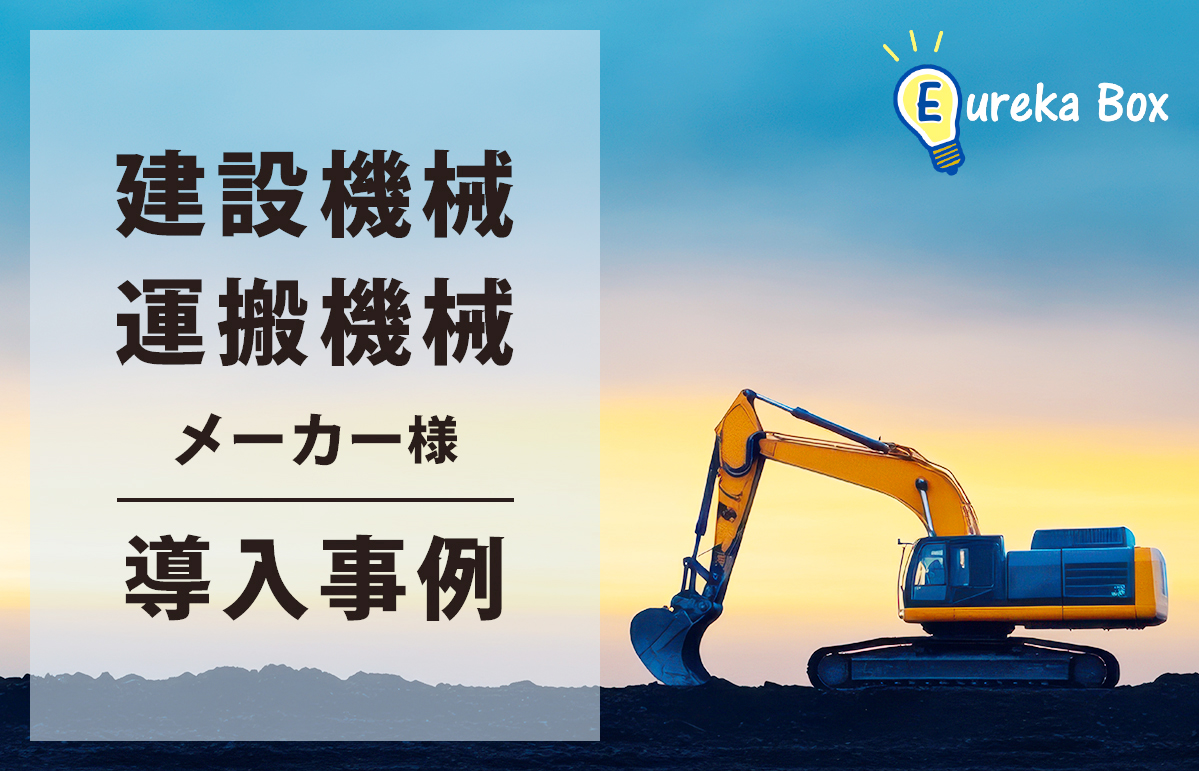トヨタ自動車系の中堅部品メーカーが語るソフト技術者の育成
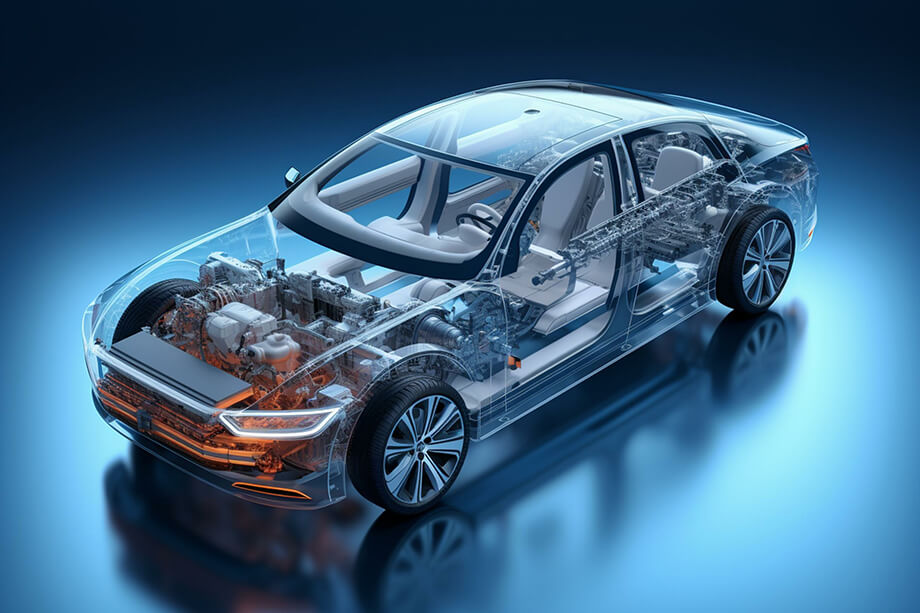
ソフトウェア人材を育成するメーカー部長が語る「企業・組織でのリスキリング・導入のポイント」
自動車業界をはじめとする多くの企業で、ソフトウェア人材が不足しており、人間力と技術力が高いエンジニアの育成が急務とされています。これを読んでいる方のなかにも、リスキリングのための研修やオンライン講座の導入を検討しているご担当者がいらっしゃるのではないでしょうか。
自社に導入できそうな教材が見つかったとしても、その後が大変です。今回は、ソフトウェアエンジニア育成に取り組んでいる愛三工業の電動システム開発本部の福森本部長に、育成プロジェクトを立ち上げた経緯と、スムーズに導入するうえで大事にしてきたことを語ってもらいました。
渡辺博之 プロフィール
株式会社エクスモーション 代表取締役社長
<主な社外活動>
情報処理推進機構(IPA)社会基盤センター 社会実装推進委員/組込みシステム技術協会(JASA)副会長、ET事業本部長、ET展示会事業運営委員長、イノベーションチャレンジ実行委員長、プラットフォーム構築委員長、組込みIoTモデリングWG主査/ETロボコン実行委員会 共同企画委員長
経営層と共有したのは「事実と危機感」
「愛三工業の機械系技術者100人をソフトウェアエンジニアとして育成する」という難易度の高いミッションと向き合った福森さんが、最初にクリアしなければならなかったハードルは、経営層の理解と支援を得ること。燃料ポンプモジュールの世界シェアNo.1を誇る自動車部品メーカーにとって、ソフトウェアという付加価値を築き上げていくこと自体が大きな決断です。
ましてや100人という大規模な人材育成となると、既存製品の製造現場にも影響があります。福森さんにいちばん聞きたかったのは、社内の危機感の高さと経営層を口説き落としたプロセスでした。
「愛三工業は、エンジン部品を主とする基幹製品がいわゆるメカ系です。今、電動カーやカーボンニュートラルが話題になっているなかで、電動シフトしていくためにはソフトウェアという付加価値が欠かせなくなっています。その人材がいないということにすごく危機感を抱いていました」
人を育てるためにリスキリングを導入するとなると、社内の利害関係者の理解促進に始まり、予算と期間の確保、納得感のある人選などさまざまなタスクをスピーディーに進めなければなりません。まずは、経営層と関係者の説得。福森さんにアプローチのポイントを聞くと、「事実と危機感の共有」という答えが返ってきました。
「まずは危機感をきちっと伝えて、経営層の合意を取らなければなりません。他社の動向や人材の状況を見える化、定量化して、これからの自動車業界や自動車部品メーカーはソフトウェア人材が揃っているのが当たり前ですよねという話をしました」
「腹落ちしてもらうために、大量のデータを集めましたね。あの会社にも、こんなにソフト人材がいるとか、ひたすらデータとエビデンスです。私たちはあくまでもメカ系で、ソフトウェアの領域に対する先入観がなかったので、データを提示したときの納得感は高かったですね。これはやらなきゃいけないねという声をいただきました」
Eureka Boxは厚生労働省が実施している助成金、人材開発支援助成金の適用対象となります。
未来を描いたからこそ得られた現場の理解
経営層の承認を得るまで2~3ヵ月と聞くと、やはり大変だなと思う人が多いでしょう。福森さんは、役員や本部長と個別にコミュニケーションを取ったほうがいいと考え、時間を取って納得感を醸成したそうです。
「全員と話したので、回るだけでも1ヵ月ぐらいかかりました。全体で話すと、なかなか個別の意見が聞けなくて、総論賛成・各論反対になってはいけないと思ったんです。個別に説明の時間を取って、納得できるま、質問に答えるという会話を繰り返しました」
「反対勢力はなかったのですが、ソフトウェアの人材が増えたら何ができるようになるんだ、会社にどういうリターンがあるんだという声は結構ありましたね。それらに対しては、事実やデータをベースとして、こういう世界を描きますというものを示して理解してもらいました」
会社としての意思決定を得て、いざ導入となると、今度は現場責任者やリスキリングの対象となる社員の理解が必要になってきます。福森さんは、基幹部品の製造や生産管理などの各本部に直接掛け合い、それぞれ何人を出せるかと話し合って人材を集めたといいます。
「育成対象は、ほぼ社内のスキル転換です。本当にやれるのかと、結構いわれましたね。社内のリソースを有効に活用しなければという話をして、25~35歳ぐらいまでの技術者を中心に集めました。100人という規模なので、現場は相当苦しかったと思います。それでも、各部門とも何とかやり切ろうという気概をもって、業務効率化と人選を進めてくれました」
現場導入の第一歩は、育成候補者の動機づけ
話を聞いていて感じるのは、経営層や部長との個別のコミュニケーションを通じて醸成された一体感と、ソフトウェア領域でキャリアアップしようとする人たちのモチベーションの高さです。何のためにやるのか、どうやるのか、やったらどうなるのかを丁寧に話したからこそ、その後のスムーズな運営があるのだと思います。
「参加者に対しては、始める前の動機づけが重要だと考え、ロードマップを示してこれから起こることを理解してもらうようにしました。電動化の世界のなかで、こういう一翼を担うんですよっていう動機づけをして、スタートしてからも定期的に個別面談を行い、ケアをしています」
「このほかにも、いろんな知見を持った社外の方に講演してもらって、ソフトウェアの必要性の理解を高めるなど、エンジニアのモチベーションが上がるような仕掛けを実施しています。同時に、なぜこの部品が必要なのか、どういうニーズに対して応えていくのかなど、お客様の困り事を技術で解決していくという思考を身に付けてもらおうと考えています」
今回紹介した以外にも、現場の声や事務局の体制などについて、福森さんにお聞きしています。この場ですべて書こうかとも考えたのですが、各論については実際の福森さんの言葉に触れていただいたほうがいいでしょう。興味がある方は、このサイトにある「ソフトウェア人材のリスキリング導入戦略と実践事例」と題した福森さんとの対談の動画をご覧ください。
ソフトウェア人材のリスキリング導入戦略と実践事例
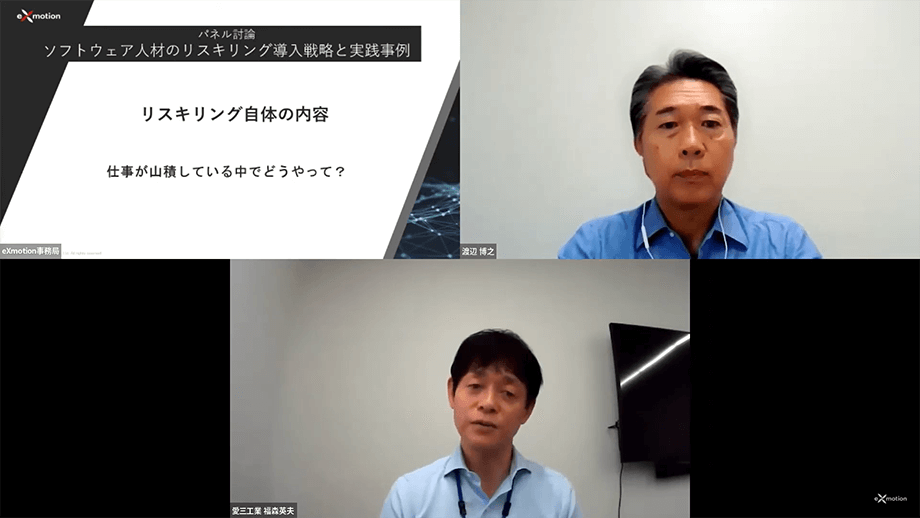
下記フォームに必須情報をご入力後に、動画をご覧いただけます。
さいごに
デジタル人材が不足している今の時代、特にソフトウェア開発の現場では「上流技術」のスキルを持つ人が必要とされています。
私達エクスモーションは、日本を代表する大手自動車メーカー、産業機器メーカー、医療機器メーカー等、「ソフトウェア開発支援」に創業から向き合い、数多くの実績を残してきた企業です。その技術ナレッジを集約させたのがオンライン学習のEureka Box(ユーリカボックス)。
今回ご紹介した愛三工業も、大規模なリスキリングのために選択したのがEureka Box。将来の企業価値を高める一助として、ぜひご活用ください。